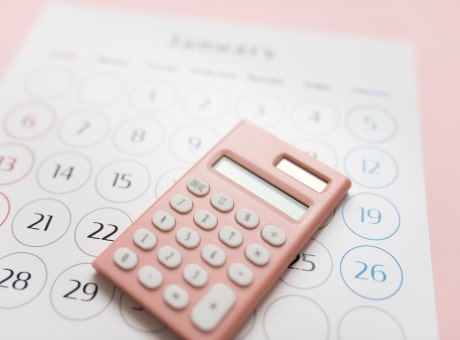垂水相続遺言相談プラザ
サポートメニュー
垂水相続遺言相談プラザは、みなさまの相続に関するお悩みをトータルにサポートします。
相続・遺言・生前対策に
ついて詳しく確認する

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。
相続の基礎知識
相談事例新着
- 2023年04月25日
- 垂水の方より死後事務委任契約の相談がありました。
- 2022年12月19日
- 年末年始の営業のお知らせ
- 2022年11月15日
- 遺言相続無料相談会のご案内(垂水区)
神戸市垂水区・西区・須磨区を中心に
相続手続き、遺言書作成等を無料相談からお手伝い

皆さまのお困り事に柔軟に対応いたします
突然の訃報に、慌ただしいお葬式が終わると、ご遺族には、早急に整理しなければならない問題が待っています。戸籍収集・遺産分割協議書作成・預貯金の解約・不動産の処分など遺産整理に必要な多くの手続きは、不慣れな方・ご多忙の方にとっては大きな負担です。
当事務所は、弁護士・司法書士・税理士等とも連携しながら相続手続の専門家として。手続面のサポートに留まらず、お客様のお気持ちに寄り添いながらお手伝いすることを心がけています。
また、当事務所では、相続手続きだけでなく、生前対策として遺言書・任意後見・死後事務委任契約書などの作成サービスも提供しております。
「相続」は「争続」とも言われますが、私はこれまでに、遺言書があれば防げた紛争をたくさん見てきました。揉めたくて揉める人など誰もいません。
大切なご家族の絆を守るためにも、是非、お早めにご検討ください。
代表行政書士 田村 実貴雄
相続のお手続きとは
相続のお手続きは多岐にわたり、ご家庭により必要な手続きも変わってまいります。そして、期限が決められている手続きもありますので、スピーディーな対応が必要となるケースもございます。何から手をつければいいのか分からず、悩んでいるうちに「期限が過ぎてしまった」という事になりかねません。
また、遺言書がない場合の相続では、相続人全員での遺産分割協議が必要であり、相続人全員で遺産分割の内容を決める必要がありますが、相続人の人数が多い場合や相続人同士の関係性が悪いケースでは、相続人間でのトラブルとなってしまうケースも少なくありません。
このような場合に、ご自身だけの判断だけで手続きを進めてしまうと、後々に不備がみつかり目的を達成することができなくなったり、また親族間でのトラブルとなってしまう可能性が高くなります。
親族間でのトラブルに発展する前に、行政書士などの専門家に相談することで解決できることは多くあります。専門家から事前にアドバイスを受けておけば、後々トラブルに巻き込まれることなく、結果スムーズに相続のお手続きが完了することに繋がります。
行政書士に依頼すると高額な費用がかかるのではないか、と心配される方も多くいらっしゃいますが、垂水相続遺言相談プラザでは相続関係のご相談は無料で承っており、無理な勧誘を行うことなども一切ございませんのでご安心ください。

垂水相続遺言相談プラザの
初回相談が無料である理由
垂水相続遺言相談プラザでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。
無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。
神戸市垂水区・西区・須磨区エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。
相続・遺言の
無料相談のご案内
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。当プラザの専門家のスケジュールを確認し、ご来所日、またはご訪問のご予約をお取りいたします。
無料相談は、ご相談にいらっしゃった皆さまのご相談時間を十分に確保するため、事前予約制とさせていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。
 STEP
STEP2
スタッフが笑顔で対応させていただきます。
ご来所される多くの方が、行政書士事務所への訪問が初めてです。
緊張される方もいらっしゃいますが、当プラザでは、スタッフ一同が笑顔で対応させていただきますので安心してご来所ください。
場所が分からない場合は、お気軽にお電話ください。丁寧にご案内させていただきます。
 STEP
STEP3
お客さまのお困り事をお聞かせください。
初回の相談は無料でお話しをお伺いしております。90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。相続の専門家が、お客様のご相談内容をしっかりと把握させていただき、今後どのようなお手続きが必要となるか、お手続きにかかる時間はどの程度なのか等、ご案内させていただきます。
ご相談は全て経験豊富な専門家が担当いたしますので、安心してご相談ください。
 STEP
STEP4
お手伝い内容や費用についても
丁寧にご案内させていただきます。
ご相談にいらっしゃる方は、行政書士などの専門家に依頼するのは初めてという方がほとんどです。そして費用についてのご不安をお持ちのままご来所されます。
垂水相続遺言相談プラザでは、不明瞭な請求項目やよくわからない手数料を頂くことはございません。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。
サポート内容とその費用について、自信をもってご案内できる内容になっておりますので、ご不明な点があればどんな些細なことでもご質問ください。